齋藤清策――日展を舞台に装飾美を求めて
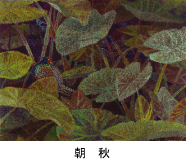 砺波野には美術館をはじめとして展示施設が複数あり、それぞれが砺波野の美術を紹介している。このコーナーを立ち上げる際に、開催中の展覧会を軸に書こうとも思ったのだが、それでは展覧会の内容に引っぱられ展評になってしまう危険があるのと、取り上げる美術家に制限をかけてしまうことにもなるので、展覧会とリンクさせるのはやめにした。だが、1月23日(日)まで庄川美術館で開催している齋藤清策遺作展がどうしても気にかかり、自分で作ったルールなのだが、あえて破っても書きたいとの思いに駆られた。会期中に原稿をアップしたい、と。それは多分、齋藤さんとの出会い――その時の印象が筆者を急かせたのだろう。
砺波野には美術館をはじめとして展示施設が複数あり、それぞれが砺波野の美術を紹介している。このコーナーを立ち上げる際に、開催中の展覧会を軸に書こうとも思ったのだが、それでは展覧会の内容に引っぱられ展評になってしまう危険があるのと、取り上げる美術家に制限をかけてしまうことにもなるので、展覧会とリンクさせるのはやめにした。だが、1月23日(日)まで庄川美術館で開催している齋藤清策遺作展がどうしても気にかかり、自分で作ったルールなのだが、あえて破っても書きたいとの思いに駆られた。会期中に原稿をアップしたい、と。それは多分、齋藤さんとの出会い――その時の印象が筆者を急かせたのだろう。
作家作品の調査で庄川のご自宅を訪ねたことがある。これももう20年も前のことである。がっしりとした体躯の齋藤さんと面と向かうと、誰もが少々圧倒されてしまうだろう。筆者もそうであった。どう切り出そうかとドギマギしていると、とても穏やかな語り口で自身の絵のこと、画家としての歩み、そして戦争体験などを、事細かに、そして実にゆっくりと語って下さった。こちらの心理状態を察してのことであったかもしれない。その後、愉快に会話が弾んだのは言うまでもない。

齋藤さんの画家の道のりを書き出すと、これまたあっという間に大量の文字で埋め尽くされてしまう。何しろ60年にも及ぶ画歴なのだ。とはいえ、何も記さないで済ますわけにもいかない。エポックといえる事項だけを拾っておこう。
1920年(大正9)に富山県庄川町(現、砺波市)に生まれた齋藤さんは、幼い頃から絵と音楽を好んだとのことである。第2次世界大戦で兵役につき、終戦後はシベリア抑留。帰国は1947年(昭和22)である。農業に従事するかたわら日本画を独学。1951年(昭和26)富山県展に初入選。1954年(昭和29)第10回記念日展に《朝秋》(図版)で初入選を果たす。1955年(昭和30)富山県展で知事賞受賞。1956年(昭和31)まで初入選以来3回連続日展入選であった。独学気鋭の新人日本画家の誕生である。さらなる高みを求めて、1957年(昭和32)に居は移さずに京都の西山翠嶂(1879~1958)に師事して青甲社に入塾。西山翠嶂が亡くなった直後の、1958年(昭和33)に西山英雄(1911~1989)に師事してグループ朴土社の一員となる。その後も日展入選を繰り返し、朴土展を舞台に作品を発表し続けた。また、富山県の日本画界のリーダーの一人として数々の重職を歴任するとともに、各方面から賞を授与されていたが、齋藤さんにとって最高の舞台である日展での特選には手が届きそうでなかなか届かずにいた。周囲の強い待望の声など意に介さない風であったようだが、当のご本人こそ忸怩たる思いに駆られていたのではないだろうか。
 念願がついにかなうのが1991年(平成3)である。改組第23回日展出品作の《山路》(富山県立近代美術館所蔵、図版)で特選を受賞する。2年後に再度、特選を受賞。その後に日展審査員を務め、1997年(平成9)に晴れて日展会員となる。2009年(平成21)に亡くなるが、前年の第40回日展まで出品を重ね(図版)、まさに斎藤さんの画業の歩みは日展とともにあった。なお、さらに詳しい画業をお知りになりたい方は、平成22年の末に上梓された『齋藤清策 画集』所収の年譜を参照いただきたい。
念願がついにかなうのが1991年(平成3)である。改組第23回日展出品作の《山路》(富山県立近代美術館所蔵、図版)で特選を受賞する。2年後に再度、特選を受賞。その後に日展審査員を務め、1997年(平成9)に晴れて日展会員となる。2009年(平成21)に亡くなるが、前年の第40回日展まで出品を重ね(図版)、まさに斎藤さんの画業の歩みは日展とともにあった。なお、さらに詳しい画業をお知りになりたい方は、平成22年の末に上梓された『齋藤清策 画集』所収の年譜を参照いただきたい。齋藤さんが美術に向き合い始めた第2次世界大戦後というと、欧米の美術動向の受容傾向が明治期を遥かに凌ぐ勢いであった。戦後の欧米では、美術スタイルの変転が一段と加速し、言論統制が解かれた日本に一挙に流れ込んだ。無反省にすべてを受け入れたとは言わないが、何か新しいものを常に欧米に求めた一面が美術界にあったことも否定できない。
この波は日本画の世界をも席巻した。美術界の中に占める日本画の地位が相対的に低下したどころか、滅亡論、不要論さえもが唱えられたのである。日本画家は日本画の危機に立ち会い、どのようにそれを超克するのかが最重要課題であった。その中にあって齋藤さんはどのように絵筆を揮ったのだろうか。
齋藤さんの画業を顧みてその特質を一語で表すならば、「一徹」という言葉が最もふさわしいように感じる。描かれたテーマは時代とともに変わっているが、どのように描くか――表現の骨子はぶれることなく長い画業に通底しているように思われる。それは停滞ではなく、微動だにしない信念であり、絵画とは何かという問いに対する齋藤さんの答えでもある。
一体、それは何か。筆者が特に惹かれる《晩秋》(富山県所蔵、図版)を見ながら、以下にまとめよう。ちなみにこの作品は、富山県議会議事堂エントランスに常陳されている。一般開放空間なので、是非とも一度見てもらいたいものだ。

《晩秋》は1973年(昭和48)の改組第5回日展出品作である。画面左上部に大きな満月、右下に月を見ようと振り向いている白狐。これらが対角の軸線を生み出す構図の作品である。が、構図の骨格であり、主題ともいえる月と白狐、さらにその関係を曖昧にしかねないほどのススキや紅葉した葉や実をつけた枝がここかしこに乱舞している。それらが画面にリズミカルな動きを与えもいるが、月の部分を除いて奥にあるべき空間をほぼ覆い隠している。すなわち画面のほぼすべてが、植物で覆い尽くされている最前景もしくは前景なのである。月とて、その大きさがもたらす印象は、遙か遠くに見えるのではなく、返って間近である。絵画空間が意識的に狭められている。
ルネサンス以降の西洋の美術が疑似視覚体験のできる合理的な絵画空間を重要な表現要素としてきたことからすると、《晩秋》は実に非西洋的な絵である。ところが、19世紀後半以降の西洋の美術が平面化を目指し、ついには非収斂、拡散、オールオーバーな画面に到達したことからすると、主題はともかくも、その表現の面では西洋のモダニズムとそれほど乖離しているわけではない。欧米の美術が日本のそれに接近したと言うべきか。
これはちょっと強引な見方かもしれない。もちろん斎藤さんご自身も欧米の美術動向をことさら意識していたわけではないだろう。前景重視の日本美術に傾倒していたのではないだろうか。それは自ずと絵画の平面化を促し、絵画の装飾性を高める。「自分は装飾的な絵を描くのだ」と主張されていたと聞く。押し寄せる欧米美術に準ぜずに、己の信じる美の道を、ひたすら一歩一歩進まれた画業であった。
(杉野秀樹・砺波市)
※氏名に「さん」を付けたのは、筆者の中でまだ歴史化されていないが故のことです。
【作品データ】
《朝秋》1954年(昭和29)紙本彩色(二曲一隻屏風)175×176㎝
《山路》1991年(平成3)紙本彩色 230×175㎝ 富山県立近代美術館所蔵
《同居の庭》2008年(平成20)紙本彩色 173×225㎝ 日展最後の出品作
《晩秋》1973年(昭和48)紙本彩色 171×230㎝ 富山県所蔵
付記
筆者にとって《晩秋》はことさら思い出深い作品である。20年前に作家作品調査で齋藤さんのお宅を訪問した目的は、ある展覧会に出品を要請するためでもあった。出品作家の一人としてリストアップしていたのだが、富山県に戻ったばかりの新参者であった筆者は「この作品を出品してほしい」とも言えず、「ご自身で代表作と思っていらっしゃる作品を」とお願いしたのである。
齋藤さんの回答は実に早かった。《晩秋》である。筆者は「おや?」と思った。15年以上も前の作品であったからだ。美術家は最新作で「今」と勝負している。齋藤さんも然りだ。だが、齋藤さんはあえて古い絵を選んだ。どうしてだろうか。疑問をぶつけると、「この作品でいけると思ったのだが・・・」と。さらに加えて「昭和48年の日展に出した作品だが、その後に手を加えているので、制作の年は昭和49年かな」と。誠に深い無念の思いがこの言葉の一語一語からにじみ出ていた。