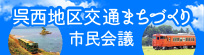木彫の町・井波 ―町筋に響く鑿を打つ槌の音(その1)
五月半ばの砺波野。水をたたえた田んぼに整然と並ぶ小さな苗。そこかしこに見られる景色だ。高台から望むと、広い平野にちりばめられた家々が水をはった田んぼに囲まれ、まるで湖面に浮かぶ無数の小島のようだ。夕暮れ時に東の小高い山から眺めると、夕日が空を茜色に染めつつ、一面の田んぼの水面に夕映えが輝く。カメラを持っていると、思わずシャッターを押してしまうだろう。それほど見事な景観だ。季節は移り、初夏を迎える頃にはまぶしい新緑の絨毯が眼下に広がり、秋にはあたり一面が黄金の稲穂の波となって、豊かな実りをこの地にもたらしてくれるだろう。
砺波野の美術家を紹介するコーナーとしてスタートしたが、さて「砺波野」とはいったい何か。平たく言えば砺波平野から「平」を抜いた略称であり、それが転じて呼称となったものであろう。とはいえ、単なる略称、呼称でもないような気がする。砺波野と言うとき、単なる地理上の境界としてではなく、自然や、歴史、文化など、そこで暮らす人々の営為をも含め、あくまでも漠然とだが、共同体として捉えて使っているような気がする。日常生活での行動において、こと細かく説明せずとも、相手のそれが何となく感覚的に分かる(と思っている)範囲と言えようか。自然、歴史、文化、風俗風習などの諸相を共有し、あるいは共有とまではいかなくても馴染みがあることで、相互理解(勘違いをも含めて)が容易なはずだ。その範囲がまずは「砺波野」ではなかろうか。
砺波平野は、庄川と小矢部川の2本の一級河川が形成した沖積扇状地である。地誌が専門ではないので、間違があればご指摘願いたいが、扇状地というだけあって扇の要を起点に河川が左右に大きく流れを変えることで肥沃な平野が形成される。治水事業で人間に飼いならされるまではまさに暴れ川。右に左に大きく流れを変えて扇状の平野部が作られる。平野の真ん中あたりに広い耕作地を確保できるとはいえ、気ままな川の流れと複雑に絡む支流で常に洪水の危険にさらされる。よって砺波野の歴史をさかのぼると、まずもって開けたのは平野と山との境界、まさに水の脅威が和らぐ場であった。例えば今石動(小矢部市)、城端(南砺市)、井波(南砺市)であり、各町の背後には小高い山が連なる地である。今石動は越中と加賀を結ぶ街道の宿場として、城端と井波は浄土真宗の寺院の門前町として発展した。
太平の世となった江戸期は飛躍的に消費が伸びた。新地開拓が進み富の集積地としての町が成立する。他所との差別化を図る独自の商品開発が促された。各町には富をもたらす産業が芽生え、それは時の衰勢で雲散霧消したものもあろうが、現在にまで引き継がれ、その地域の看板になっている伝統産業もある。
井波の木彫の歴史と伝統は町の起こりのである瑞泉寺とともにあったといってよい。同寺は、1390年(明徳元)に後小松天皇の勅許の命が下り、本願寺五代綽如上人によって創設されたが、その後の火災で何度か消失している。特に1762年(宝暦12)の井波大火による類焼の被害は甚大であった。再建は10年ほど後のことになり、本堂彫刻のため京都本願寺より御用彫刻師の前川三四郎が井波の地に派遣された。このとき地元大工らも加わり、前川三四郎の木彫の技を習得したのが、井波木彫の起源と言われている。仏閣を飾る装飾木彫や家を飾る欄間製作を生業とした職人集団が技を競い、技量を磨いてきた。戦後、長年にわたり培ってきた木彫技術をベースに、若者たちのチャレンジが始まる。
(杉野秀樹・砺波市)