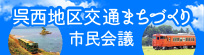増山城最後の城主中川宗半(光重)と蕭 老松邦雄
はじめに
平成17年春の砺波郷土資料館特別展は、「戦国の山城増山城ものがたり」と題して、富山県指定文化財(史跡)である増山城をさまざまな角度から取り上げた。そのひとつが、最後の城主であった中川宗半(光重)の事跡であった。
幸い、宗半を第一祖とし加賀藩で代々五千石を給された中川家(中川八郎右衛門家として後述)の後裔の方が、隣接の南砺市に在住で、宗半宛の前田利長書状や系図などの古文書が残されている。それらの一部は、平成2年刊の『砺波市史資料編 1』に取り上げられているが、系図などについては触れられていない。
ここでは、中川家に伝来する『中川家系図』や、「増山城ものがたり」展の際整理した諸記録の記述を中心に、増山城最後の城主中川宗半(光重)とその妻蕭(しょう)の事跡を紹介してみたい。
生 誕
『中川家系図』によると、中川宗半(光重)は、桶狭間の戦いの二年後、永禄5年(1562)に織田信長麾下の中川重政の二男として生誕した。若名は清六または清六郎、のち光重を名乗り、さらに宗半または巨海斎と号した。中川氏は清和源氏小笠原氏 の系譜で、宗半(光重)の曽祖父清政の代に尾張に来て中川氏を名乗った。宗半の父中川重政は織田刑部少輔の子で、はじめ織田駿河守を号し、のち中川次郎左衛門の養子となって中川八郎右衛門を名乗ったとしている。また、『加賀藩史稿中川光重(清六)列伝』(以降『光重列伝』とい う)では、中川氏は斯波尾張守高経の裔であるとしている。
中川重政は、織田信長に仕え、黒母衣衆の一人に名を連ねて活躍した。赤母衣衆・黒母衣衆は、永 禄年間織田信長が近臣の中から「戦功の衆」20名を選抜し作った職掌で、前田利家・佐々成政らを輩出しており、重政はこれらの武将と同列の織田軍 団の中枢の一人であった。
特に、信長が足利義昭を擁して上洛した翌年の永禄12年(1569)には、丹羽長重・木下秀吉・明智光秀とともに京都・畿内の行政官に抜擢されており、四名連名の文書が同年4月から翌13年(1570)3月まで残されている。次いで、13年5月ころには近 江蒲生郡安土城を任され、翌元亀2年(1571)ころには蒲生郡と神埼郡の一部を宛行がわれていたようである。しかし、元亀3年(1572)8 月、領地の隣接していた柴田勝家と刃傷沙汰を起こし、改易されたという。その後については不明で、没年などは明らかになっていない。
宗半(光重)の妻蕭は、宗半生誕の翌年、永禄6年(1563)に生まれた。③父は加賀百万石の祖前田利家、母はその正室まつ(芳春院)で、第一子長女幸、第二子長男利長に次ぐ第三子であった。当時利家は、信長の勘気を解かれて二年目で、信長近 習の一人として美濃攻めなどに活躍していた頃であった。
蕭は、将・昌・粧などの字を当てられることもある。中川家に伝わる伝承では、蕭姫は非常に美人で、豊臣秀吉が側室として望んだが果たされず、その際秀吉から蕭姫に贈られた玉が中川家に伝世していたという。
増山城の城主に
『中川家系図』や『光重列伝』によると、中川光重は、天正10年(1582)織田信忠に従って信濃高遠城を囲み、功があったとしている。『中川家系図』ではそのとき光重14歳としているが、享年から逆算すると、21歳(数え)のときとなる。まも なく前田利家の二女蕭姫を娶り、信長逝去後、利家の下に来て仕えたとしている。
『三壷記』や『管君雜録』などには、天正3年(1575)に利家が越前府中で三万三千石を拝領した際、 尾張荒子から移ってきた御家中衆いわゆる府中衆の一人として「中川武蔵」(三壷記)、「中川清六光重貳百石」(管君雜録)の記載があるが、当時光 重は14歳であった。『中川家系図』『神谷外記先祖由緒並一類附帳』(以降『神谷由緒書』という)などにあるように、天正10年6月信長 死去の後、当時能登一国の国持ち大名で、信頼のおける武将を求めていた前田利家の配下となった、とするほうが無理がない。
天正11年(1583)、賎ヶ岳の戦いで羽柴秀吉勢が勝利した後、前田利家は秀吉幕下に入り、能登一国に加え加賀の石川郡・河北郡の二郡を与えられ、本拠を金沢城に移した。このころ中川光重は、前田安勝・高畠定吉とともに七尾城の守将となって いたという記録がある。(『末森記』)
天正12年(1584)、羽柴秀吉と徳川家康との間に小牧長久手の戦いが勃発すると、前田利家と越中の佐々成政との間が不穏となり、9月には両勢が末森城を挟んで激突した末森合戦が起った。翌13年(1585)6月、七尾城の軍勢は能越国境の 荒山城を攻め落とし、その際中川光重に功があったとされている。(『末森記』)
その年8月には秀吉の越中出陣、成政の降伏があり、前田利長に砺波・射水・婦負の三郡が与えられた。このころの守将配置については「前田右近(秀継)父子越中木舟へ移。益山(増山)に山崎閑斎、氷見に菊池伊豆、利長公も森山(守山)へ御 移」(『前田家雑録』)という記録がある。また、天正15年(1587)、秀吉の九州攻めで利家・利長ともに金沢を留守にした際には、金沢 に前田安勝、七尾城に前田利好・高畠織部・中川清六が、増山城には片山伊賀が配されたとされている。(『越登賀三州志』)
しかし、天正14年(1586)、越後の上杉景勝が上洛する際の記録『上杉景勝上洛日帳』には、「五月廿七日御立、於中田、増山之武主中川清六殿新造を御立、(中略)御一献被相勤、御腰物進上被申候」と、「増山之武主」である中川清六(光重)が 中田において景勝を饗応したと記されている。おそらく越中三郡を前田家が領有して間もないころに、中川光重が増山城を任されたのではなか ろうか。
能登津向(つむぎ)村に蟄居
『光重列伝』には、天正17年(1589)11月、光重が修城の課役を怠り、「遂ニ之ヲ能登津向村鹿島郡二謫ス」という事件を記載している。これについて、『神谷由緒書』には「能州津向被指置」、『中川家系図』には「能州津向ニ在住」と記されている。
津向村は現在の七尾市津向で、天正10年(1582)利家が築城した七尾小丸山城の北西側に位置し、利家が七尾の防衛のため寺院を集めたといういわゆる山の寺寺院群の近くである。とすると、「津向村二謫ス」は配流されたというより、蟄居と いったほうがふさわしいようである。
この津向村流謫は、天正17年のこととすると、この年前田利家は七尾城の修築をしきりに命じており、『砺波市史資料編1』は「光重の修城懈怠は七尾城にかかわるものであったと考えられる」としている。
しかし、前田利家の生年が推定できることで有名な気多大社蔵の『前田家戦勝祈願依頼状』は、天 正18年(1590)のものとされ、「こんとの御ちん(陣)、としいゑさま五十四、としながさま廿九、(中略)ちん七郎様(前田長種)、むさしと の(中川光重)の御きたうのために候」と、利家・利長父子とともに利家息女の二人の夫の武運長久を祈ったものである。天正18年の陣となると、利家が北国方面の総大将となった関東の北条攻めで、出陣はその年2月である。つまり、蟄居の翌年早々に光重は関東攻めに参陣していることになり、蟄 居が極めて形式的なものであったか、年代にずれがあるかのどちらかであろう。
文禄4年(1595)7月、秀吉の甥豊臣秀次が関白を廃され自刃する事件が起こるが、その前の6月に秀次に深くかかわった浅野幸長が能登に配流された。そのとき利家から能登の三輪藤兵衛にあてた文書に「尚々武蔵家せばく、不自由成所々は、家も 作り可申候、以上。態申遣候。仍左京太夫(浅野幸長)先々能州へ御下候て、少之間住宅事候。然ば武蔵家を相渡し可置候。(中略)武蔵女共 は我等屋敷へ移し可置候(後略)」とある。他の資料でも浅野幸長は能登鹿島郡津向に置かれたとされており、この文書にあるように「武蔵家」(中川 光重宅)が配流先として利用されたようである。つまり、この時期(文禄4年6月)中川光重は、津向村蟄居中であったかまたは豊臣秀吉の譚 伴(御伽衆)となっていたということになるが、『豊太閤前田亭御成次第』では、その前年の文禄3年(1594)4月8日、京都の前田利家邸に豊臣 秀吉が来臨した際に、光重は前田家臣団の筆頭で、秀吉に太刀一腰・御馬代三百疋・杉原百帖・蝋燭百廷を献じたと記録されている。とすると、「光重修城ノ課役ヲ懈リ、津向村ニ謫ス」事件は、文禄3年(1594)4月から翌4年6月の間に起こった可能性が高いということになる。
さて、『光重列伝』では、津向村流謫の後いくばくもなく関白秀吉に仕えて「譚伴(御伽衆)」となり、 三千石を給されたという。そして「復タ来リ事フ」再び前田家に復帰したとしている。
では、前田家に復帰した時期はいつごろであろうか。『村井重頼覚書』では、慶長元年(1596)8月には「武蔵はらう人ゆゑ」と浪人中であったとしており、慶長元年8月段階でまだ前田家に復帰していなかった可能性がある。その場合でも、後述する ように慶長4年(1599)3月には利家の子の養育係を勤めており(後述)、慶長期の早い時期には前田家に復帰したものと考えられる。
蕭姫増山城を守る
旧砺波郡内には、増山城から発された文書が三通残されている。一通は砺波市太田の加賀藩初期十村役金子家に残されている『法印宛志めのゑん安堵につき書状』で、あと二通は高岡市荒見崎の社家榊原家に残されている『十禅師無役につき書状』と 『福田村神主無役につき書状』である。
金子文書のものは、「ほういん(千光寺)」に対し「志めのゑん」の地を従来どおり寄進地とし検地 役人に申し入れた旨伝えた断り状で、「十一月廿二日」の日付で、差出は「ますやま城より」とし、黒印(左から「貞蕭」と読める)が押されている。 榊原文書はいずれも福田村神主駿河に利長子女の祈願を命じ、諸役免除の特権を約したものである。「十せし」宛てのものは「ふんろく二ねん (文禄2年1593)八月九日」の日付で、差出には金子文書と同じ黒印が押され「さい将」と書かれている。「ふくたむらかんぬしするか」宛てのも のは「ふんろく二ねん十月十四日」、差出は「ますやまさいしやう」で花押が書かれている。この「さい」は、あるいは「貞」のくずしとも見ることができ、であるとすると「さい将」「さいしやう」は黒印の「貞蕭」と一致する。なお、蕭の法名は「貞芳」であり、これも「貞蕭」に通ずるも のがある。
これらは、いずれも当時中川光重不在中の増山城から、蕭姫が差し出したものとされている。それでは、なぜ中川光重が増山城不在であったか。『砺波市史資料編1』では、津向村に流謫され、ついで秀吉に御伽衆として仕えた時期としている。しかし、先ほど記したように、文禄2年にはまだ津向村流謫となっていない可能性が高い。
文禄元年(1592)2月、前田利家は豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)のため金沢をたち、その後翌2年(1593)11月金沢へ帰還するまで、名護屋に滞陣しその後京都に滞在していた。『国祖遺言』には名護屋出陣の前田家武将の中に「中川清 六」の名があり、光重が名護屋滞陣の間、妻蕭姫が増山城を守っていたのかもしれない。
その後、光重の津向村流謫があり、蕭も同行したとすれば、先述の「武蔵女共は我等屋敷へ移し可置候」つまり、浅野幸長配流先に中川光重宅を充てることとし、武蔵女共つまり蕭たちを利家の屋敷に移しなさいという内容と矛盾しない。
増山城の主郭通称「二の丸」には、中央を丸く抉った「神水鉢」と呼ばれる石が置かれている。最近の城郭研究家高岡徹氏の研究によると、肥前名護屋城周辺にこれによく似た石がいくつも残されており、現地では旗竿石と呼ばれているように、おそらく軍旗や馬印を立てるために使われた台石であろうとされている。前田家陣屋跡にも二基残されており、増山城の神水鉢は名護屋での習わしを宗半が持ち込んだものと考えられている。宗半不在の増山城を守った蕭に対し、名護屋で流行した旗立ての行事を宗半が披露した、としたら推測が過 ぎるであろうか。
さて、蕭姫は、『前田氏系譜』によると「後因所居之地名。呼稱増山」とされ、住んでいるところに因み、増山殿と呼ばれていた。蕭には宗半(光重)との間に二人の娘がいたと推測され、『中川家系図』によると、長女は神谷信濃守に嫁し、次女は中 川家の家督を継承した宗半(光重)のおい中川長勝の室であった。
慶長4年(1599)閏3月、前田利家が没すると、遺品として金子七十枚、絹三十疋、綿二百把が「宗 半御うへおしやう様へ」遣わされている。
慶長8年(1603)11月29日、城主宗半(光重)が留守がちであった増山城を守り、「増山殿」と呼ばれた蕭姫は、享年41歳で歿した。
宗半の密書
中川宗半(光重)は前田家復帰後、二万三千石の重鎮として家中に重きをなしていった。慶長4年(1599)3月、前田利家が夫人に遺物配分を記させた記録には「金子七拾枚。此内、ゆするきの御子三十枚、信濃取立申御子廿枚、宗半御取立の御 子廿枚」とある。「ゆするきの御子」は石動山に入った利家三男の知好と考えられ、四男利常については別に「御さる様」とあるので、宗半は 利家五男利孝または六男利貞の養育係となっていた可能性が高い。なお、利家死去に際し、宗半も遺品として金子五枚・小袖五つを賜っている。
同年閏3月前田利家が死去し、その年8月には前田利長が金沢へ帰還した。その際利長は、宗半と村井長頼を大坂に残し、豊臣秀頼と芳春院のことを託したという。(『享保雑誌』『三壷記』)
翌慶長5年(1600)5月、芳春院は人質として江戸へ下り、9月には関が原の戦いが起きた。前田利長は徳川方につき、同年8月西軍方の大聖寺城を攻略し、金沢へ引き返す際、小松城の丹羽勢と浅井畷で衝突した。『光重列伝』では、宗半は前田利政 に属し、大聖寺城攻略に戦功があったという。
前田軍が金沢に引き返した理由は、宗半からの密書があったためという説がある。少し長いが『可観小説』の一部を引用する。
「此時利長一族に中川宗半といふ者、秀頼近習の伽の衆也。大坂より加賀へ通候を大谷聞付、人を出し宗半を推留、是非をいはせず謀書をかゝせ候。其詞に云。
此度北國筋大谷刑部請取、四萬餘に而取向候。一萬七千は北荘口より推詰、三萬は船手に而大廻を仕、加州へ着岸し、金澤を可攻取催しに而候條、御油斷不可有之候、恐々謹言。
八月三日中川宗半
肥前守殿
右之通認書候。中川は希代の能書に而紛無之候。(中略)利長は宗半自筆無疑ければ大に駭き、八月七日大正寺を引拂、金澤へ引取」
ここでは、宗半が大阪から加賀へ向かおうとして、越前敦賀城主大谷吉継に捕えられ、四万余の大軍が加賀を攻めるという書状を書かせられた。それが利長の元に届き、宗半自筆に間違いなかったので利長は大いに驚き、大聖寺を引き払って金沢に帰 還した、としているわけである。
一方、『前田出雲覚書』や『袂草』などでは、大軍が加賀を攻めるという戸田武蔵守からの偽の情報により引き返したとしている。『袂草』では、「是中川武蔵と云説有。中川は十年前宗半に成、其上今度御供也」と、中川宗半は前田軍に従軍してお り、さらに10年前から宗半と名乗っていることから、戸田武蔵守と混同したのではないか、としている。
また、中川家文書の中にある『故々八郎左衛門長勝物語覚書』を要約すると、「宗半は美濃で戸田 武蔵守と会った。戸田武蔵は、利長が南下した場合、小松・大聖寺の丹羽・山口が帰路をさえぎり前田軍は挟み撃ちとなること、すでに関が原で東西対 決があり東軍が敗北したこと、などを話した。宗半がその旨利長に注進したところ、利長は金沢に帰陣する際、丹羽長重を攻め潰した。宗半は その功により二万七千石を賜った」となる。このような話が中川家に伝承していたわけで、あるいは宗半は、大坂・京都の状況や西軍の動向などを金沢 に知らせる任務を担っていたのかもしれない。そして、利長は小松城の丹羽長重の離反に気が付いておらず、宗半の情報が大いに役立った、と いうのが意外と真相なのかもしれない。
なお、同年9月3日付の利長から村井長頼にあてた書状では、「(八月)三日に大聖寺城を攻め滅ぼしさらに越前へ攻め懸けようとしたが、伏見城が(八月)一日に落城し、さらに越後でも一揆が起こったという注進があった」としており、この書状 から一般的には、偽情報のため前田軍が金沢へ帰還したという説は、否定されている。
巨海斎宗半
中川光重が「宗半」を名乗ったのはいつごろであろうか。『光重列伝』や『中川家系図』、『神谷由緒書』ではいずれも慶長16年(1611)退老して宗半または巨海斎と号したとある。しかし、慶長4年(1599)3月、『前田利家遺言状』に 「宗半娘」とあり、そのころまでには宗半が通称となっていたようである。また、『袂草』には慶長5年(1600)関が原の戦い前後の記載の中に 「中川は十年前に宗半になり」と天正18年(1590)ころから宗半と号していたとしている。
「武蔵」については、『光重列伝』では文禄3年(1593)、光重は従五位下に叙され武蔵守に任じられたとしている。ただし、すでに天正16年(1588)聚楽第行幸の際に「中川武蔵守」の名があり(『聚楽行幸記』)、前述天正18年 (1590)気多大社蔵『前田家戦勝祈願依頼状』には「むさしとの」とあり、すでに天正年間から武蔵を名乗っていたものと考えられる。
さて、慶長7年(1602)5月、金沢城内で太田但馬守長知が、横山大膳長知に上意により誅されるという事件が勃発した。その原因ははっきりしていないが、親徳川派と反徳川派の派閥抗争のようなものであったろうといわれている。『象賢紀略』に よると、宗半は反徳川方とみなされていた太田但馬派で、その筆頭に名を挙げられている。
しかし、この事件後も、宗半の前田家重臣としての地位は揺るがなかった。同年7月、金沢城天守閣や本丸が消失した火災の際には、中川宗半宅に城の女中衆が避難している。(『三壷記』ほか)文書では、慶長8年(1603)6月16日付の『井 波山相論につき裁許状』では長九郎左衛門尉連龍らとともに巨海斎宗半の署名があり、さらに砺波市鹿島の河合文書の中の9月16日付(慶長 10年か)『苗加村と野村嶋野境相論につき裁許状』では、横山大膳職長知らとともに巨海斎宗半の署名がある。慶長11年(1606)羽咋村の諸役 を免じ?釜役を命じた文書や同13年(1608)2月脱走した農民を穿鑿する等の法令などにも、南坊等伯(高山右近)などとともに巨海斎宗半の名がある。
『中川家系図』『神谷由緒書』『光重列伝』では、慶長16年(1611)2月2日、宗半は隠居領五千石を賜り退老したという。ただし、中川家文書のうち前田利光(利常)から宗半宛の『隠居分知行状』では、同日付けで領地のうち二千石を隠居分として宛 行うとしている。同じ日付で嗣子忠光に一万七千石、養子長勝に四千石が、宗半知行分から加増されており、二千石と合わせるとちょうど二万 三千石になる。知行状にあるように、宗半隠居領は二千石であったのであったのかもしれない。
宗半には、武将と茶人の二つの顔があった。茶人としては千利休門下で、何度も利休から茶会に招かれている。能登津向村配流は、茶会に没頭し修城の課役を怠ったためとされており、豊臣秀吉の御伽衆についても、茶人としての拝命であったとされ ている。なお、前田利長から与えられのち返却した名物茶入れで宗半の名を付した「宗半肩衝」が、金沢市中村記念館に保存されている。
慶長19年(1614)11月21日、宗半は享年53歳でこの世を去った。大坂冬の陣で騒然としている時期であった。『越中古城記』には「中川宗半者於此城卒去」とあり、また、寛政4年(1792)5月12日付けの下川崎村十左衛門の文書では「則宗 半殿御卒去の砌、此所(恩光寺旧地)之墓所に葬申旨に御座候」とあり、宗半は増山城において歿したとも考えられる。
ただし、平成18年3月2日から4月23日まで射水市新湊博物館で開催された「最古の国絵図を読む—越中・加賀・能登」展で、写真パネルとして展示された東京大学総合図書館所蔵の『越中国絵図』には、「五福山の古城」に続く丘陵の西端に「増 山古城」が記載され、和田川を隔てて「増山町」の地名がある。この『越中国絵図』は、慶長10年(1605)の作とされており、「古城」 の記載から絵地図製作時には増山城は廃城となっていた可能性が高い。
ともあれ、砺波市庄金剛寺の恩光寺(現南砺市福野)旧地近くには、宗半を葬ったと伝えられる「宗半塚」があり、金沢市野田山の中川家墓地には、光重と蕭の墓碑が石室の中に静かに眠っている。
その後の中川家
ここでは、主に中川宗半(光重)と蕭の子孫や関係する家系について触れたい。なお、主に『中川家系図』の記述により、各家の名称は分立した最初の人の名を取った。
[中川八郎右衛門家]
後述するように宗半の嫡子中川光忠が加賀藩を致仕したのち、中川家の家督を継承したのは宗半の養子中川長勝であった。中川長勝は、宗半の弟中川半左衛門忠勝の長男で、天正11年(1583)生まれ。慶長元年(1596)14歳のとき宗半の 養子として加賀へ来たとされている。明暦2年(1656)74歳で歿した。長勝の父中川忠勝は豊臣秀吉に仕え、関が原の戦いで東軍に組みし、のち徳川家の旗本となって美濃国で三千石を領した。元和元年(1615)福島正則が改易となった際、広島城開城の御使となり、寛永5年 (1628)には山田奉行に任じられている。(『寛政重修諸家譜』以後『寛政譜』という)
中川長勝の若名は佐左衛門または三左衛門で、のち祖父の名八郎右衛門を名乗り、ほかに宮内を名乗った。室は宗半二女で、『中川家系図』には「瑞雲院様(蕭)之御子也」と記されている。金沢市立玉川図書館の近世史料館に所蔵されている『中川 典克所蔵古文書』には、「はひ」(利長)からおひさ宛「いきみたま(生きている父母などへの盆の贈り物)の礼状」のほか、「ひ」(利長) や「ちくせん」(利常)、「はう」(芳春院)から「おひさ」にあてた書状が収録されており、この「おひさ」が宗半二女である。
中川家には、代々の知行宛行状が残されているが、最も古いものが慶長4年(1599)8月13日付『越中加州内を以八百俵令扶助畢」という前田利長から中川佐左衛門(長勝)に宛てたものである。(『砺波市史資料編1』ではこの文書を中川宗半宛のも のとしているが、写真を元に読み下したため「宛所がない」と誤認し、宗半宛と判断したものと思われる)
以降、長勝は慶長6年(1601)7月二百石、同7年9月二百石、同9年8月二百石と加増され、慶長16 年(1611)2月宗半隠居に伴いその知行地のうち四千石を加増されて計五千石を領した。
慶長19年(1614)10月、大坂冬の陣に前田利常が出陣した際、中川大隈(光忠)の名代として中川宮内(長勝)の名がある。(『大坂出陣覚書』)また、『中川家系図』では『元和元年(1615)五月大坂御陣之時出陣モキ付首執」と大坂夏の陣で 活躍したとしている。
中川家三代目長種は、長勝の妹が嫁した瀬川蔵人の子で、慶長15年(1610)生まれ、元禄14年 (1701)92歳で歿した。系図では大横目役に任じられていたという。以降、この家系は代々五千石を拝領し、加賀藩家老職などを歴任するが、こ の家系の代々と加賀藩における主な役職をあげると次のようになる。
四代長輝 寛永15年(1638)〜元禄13年(1700)
定火消役、宝円寺請取火消
五代長定 延宝2年(1674)〜元文4年(1739)
新堂形請取火消、神護寺請取火消、定火消役、若年寄、家老
六代惟忠 正徳5年(1715)〜宝暦7年(1757)
定火消役、家老
七代寄忠 寛保元年(1741)〜天明5年(1785)
定火消役、寺社奉行兼公事場奉行
八代顕忠 安永3年(1774)〜文化12年(1815)
定火消役、寺社奉行兼公事場奉行、家老
九代典義 寛政10年(1798)〜慶応3年(1867)
定火消役、寺社奉行、若年寄、家老
十代典惇 文政10年(1827)〜明治3年(1870)
定火消役、寺社奉行
[神谷冶部家]
慶長18年(1613)、宗半の嫡子中川光忠が、故あって京都へ立退き浪人となるという事件が起こった。宗半が歿する慶長19年(1614)の前年である。
中川光忠は、『神谷由緒書』によると、はじめ千五百石で前田利政に仕え、次いで前田利長の配下となって四千石まで加増され、さらに慶長16年2月、宗半の引退に伴い宗半所領のうち一万七千石を加増され、計二万一千石を拝領した。光忠には、 長好連と死別していた前田利家の八女福が再嫁した。(長好連は慶長16年に死去している)
『神谷由緒書』では神谷家の十世の祖父を中川光重、十世之祖母を瑞雲院(蕭)とし、『前田氏系譜』にも蕭には「生一男二女」とあり、光忠が蕭の実子である可能性もある。しかし、蕭の妹である福を娶っていることや、『加賀藩史料』の慶長16 年『慶長以来定書』の注に「宗半は中川光重、大隈はその弟にして嗣たる光忠」とあり、『加賀藩史料』では光忠を宗半の弟と認識していたようである。また、利家遺物配分の記録の利家長女幸の項に「此内御子様達へも」とされているのに対し、蕭の項には「此内御息女様へも」とされてお り、蕭には男の子はいなかった可能性が高い。
光忠が京都へ立退いた理由については、『神谷由緒書』にも『中川家系図』にも「故有テ」としか 記載されておらず不明である。一説には、利家の娘である福と合わず離別したためという。また、慶長7年(1602)金沢城内で太田但馬が上意によ り横山長知に誅されるという事件が起こっているが、中川宗半は太田但馬方であったと目されており(象賢紀略)、そうした派閥争いが原因と いう推測もある。
いずれにしても、慶長18年(1613)8月の『白山大神宮撞鐘御奉加帳』に「銀子一枚 中川大隈守」とあるので、この年8月以降に「京都江立退」く事件が起こったものと思われる。
さて、『神谷由緒書』によると、光忠の嫡子冶部元易(『中川家系図』では之尚)は、光忠浪人後、光忠の妹婿である神谷信濃守に養育されたという。神谷信濃守の室については、慶長4年(1599)3月前田利家が利長に宛てた遺言状の末尾に「神 谷信濃方へ宗半娘可遣かと、おせう被申候間、貴殿分別次第ニ候事」とあり、宗半の娘が神谷信濃守へ嫁したもので、『神谷家譜』には、「信 濃守妻献珠院は高徳院様(利家)御孫娘」つまり蕭の娘であるとしている。
元易(之尚)はその後神谷を名乗り、寛永7年(1630)三千石を給された。さらに同16年(1639)大聖寺藩の家老として同地へ移った。以降この家系は二代内膳守政、三代内膳守應と三代に渡り大聖寺藩の家老を勤め、三代神谷 守應のとき加賀藩に復帰した。この家系は、明治維新時、千五百石の家格であった。
[中川弥左衛門家]
光忠のもう一子、中川弥左衛門正任については、「大隈浪々之後年有テ」加賀藩に召出された。は じめ三百石でのち四百石に加増されたという。
この家系と中川八郎右衛門家はたびたび養子縁組をしている。たとえば、三代長種の四男が中川正 任の養子として弥左衛門家二代となっている。また、文化12年(1815) 八郎右衛門家八代の顕忠が江戸で病死した際には、正任から四代後の中川従父の嫡子が顕忠の末期養子となり、八郎右衛門家九代 を継いでいる。この家系は明治維新時においても四百石の家格であった。
[中川半左衛門家]
中川宗家二代長勝のところで触れたように、宗半の弟中川忠勝は、徳川家旗本となったが、その跡は忠勝の三男で長勝の弟元重が父と同じ半左衛門を名乗って三千石を継いだ。『寛政譜』によると、中川元重(『寛政譜』では「光重」)は、元和元年 (1615)大坂夏の陣に参陣し兜首の首級を挙げたとされ、さらに寛永17年には御使として加賀国に赴いている。
三代重勝の代に弟勝宗に五百石を分け、新開を合わせて二千六百七十石となった。中川勝宗の系統 は二代で絶えている。四代成慶は大目付からさらに職禄五千石の御留守居まで昇進し、従五位下伊勢守または淡路守に叙任された。五代忠利は、高禄の 旗本が列せられる寄合となり、妻は大岡越前守忠相の娘であった。
なお、天保8年(1837)2月、大阪において大塩平八郎の乱が起こるが、その際大坂城目付代に「中川半左衛門」がいて状況を江戸に知らせた文書が残っている。また、森鴎外の小説『大塩平八郎』にも「目附中川半左衛門」が登場する。名前から見る と、ひょっとしたらこの家系の人かもしれない。
[中川七兵衛家]
中川元重の男子のうち、重勝が半左衛門の名跡を継ぎ、勝宗は分家して徳川家に仕え、七兵衛重良は承応3年(1654)加賀藩五代藩主前田綱紀のとき、加賀藩に召出され千石を給された。
この中川七兵衛家も他の中川家などからたびたび養子を受け入れている。七兵衛家三代の久充は中川弥左衛門家三代長時の三男、五代忠好は中川八郎右衛門家六代惟忠四男であった。この家系も明治維新時まで続き、同じく千石の家格であった。