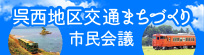川辺外治 ―絵が伝える、ある画家の晩年の生き様
回顧展ならば、代表作と目される作品はいうに及ばず、若描きの絵から晩年までの仕事が網羅され、画業の変遷を見ることができる。しかし、回顧展は何か特別なタイミングで開かれるのであって、各時代の作品を一堂に見るチャンスはめったにない。そのために代表作と評される作品がさまざまな場面で使われることになる。そしていつしか代表作だけで作家の全体像が括られる。とはいえ、それが不幸だとはいえないだろう。代表作としてメディアに取り上げられたり、代表作が美術館に納まったりする美術家は選ばれた極少数派だからだ。それを承知の上で、是非ともその生き様、特に晩年の姿を紹介したい画家がいる。川辺外治である。
この作品では、農家の日常風景をスナップ写真で撮ったかのようなシーンが描かれている。穏健な写実主義に立脚している。その後も《早春》(1941年)や《藁仕事の母子》(1943年、写真上)といった油絵で、農村の厳しいながらも、どこかほのぼのとした生活情景を描出した。川辺外治の作品といえば、まずもってこの時期の絵が持ち出される。これらを抜き、川辺芸術の紹介は成立しない。画業の出発点であり、代表作である。だが、川辺の創造の道のりはこの後、まだ40年も続く。
その間、画家川辺の生き様において、筆者の目を引くのは、1958年(昭和33)の彩彫会の結成と、同年に《石燈籠の見える石屋》(1958年)を日展に出品したのを最後に同展から離れるという二つの事項である。戦後、砺波野の美術展開において重大な役割を果たした彩彫会については、別に稿を起そうと思っているが、同会の結成と日展からの離脱とが同時期なのは単なる偶然ではあるまい。日展という場が、己の表現に何がしかの足かせを課しているのではないか。表現の制約と窮屈さを感じるようになってしまったのではないか。その場を飛び出す他ない。画家57歳の決断であった。
それまでも近代美術の巨匠の研究を重ね、絵の端々にその成果を見せる作品を発表していたが、1960年代後半に入るとジャコメッティの作品に感化を受け、モデルを真正面から観察するとともに、モデルを取り巻く空間を意識した作品を制作する。それは単なる影響の域に留まるものではなく、モデルと空間に関してジャコメッティ作品の、川辺流の再解釈であり、その成果が《老人》(1970年)や《農婦》(1971年、写真中)であった。
川辺はここに留まらない。パウル・クレーの研究に邁進する。形象の単純化、記号化、そして色彩の象徴化を試みる。もうすでに最晩年といえるが、新しい表現法を探ろうとする川辺のパイオニア精神は全く衰えを見せない。それどころか若々しくさえある。
不安を描き、葛藤を描き、叫びと嘆きを描く。そして黒い太陽シリーズへ。黒い太陽、さらに太陽を取り囲む配色は不気味で不穏である。光を失った太陽は、人間存在に対する川辺の絶望感を象徴しているのだろうか、底しれぬ人間の闇を感じさせる。他方、負の方向へ傾く絵画に対して、《大空に生きる》(1982年)、《精霊の舞》(1983年)や《涅槃の里》(1983年)で求めたのは、多分、希望であり、救いであり、生の全面的な肯定であったろう。
絵で何を表し得るか、絵で何を表さなければいけないか。年を重ねれば重ねるほど、思想は深化し、実践の場で激しく格闘した。その軌跡が残された絵画であり、画家としていかに生きるべきかを諭す。川辺外治の晩年の作品は、同じ道を歩もうとする若者を励まし導く道標となるに違いない。
(杉野秀樹・砺波市)
《黒い太陽(落日)》
【図版】データ
《藁仕事の母子》1943年 キャンバス・油絵具 80.3×100.0cm 砺波市美術館所蔵
《農婦》1971年 キャンバス・油絵具 116.7×80.3cm 砺波市美術館所蔵
《黒い太陽(落日)》 1980年 キャンバス・油絵具 91.0×72.7cm 砺波市所蔵
砺波市美術館「川辺外治の軌跡展」図録、1997年